記憶を辿る 102話
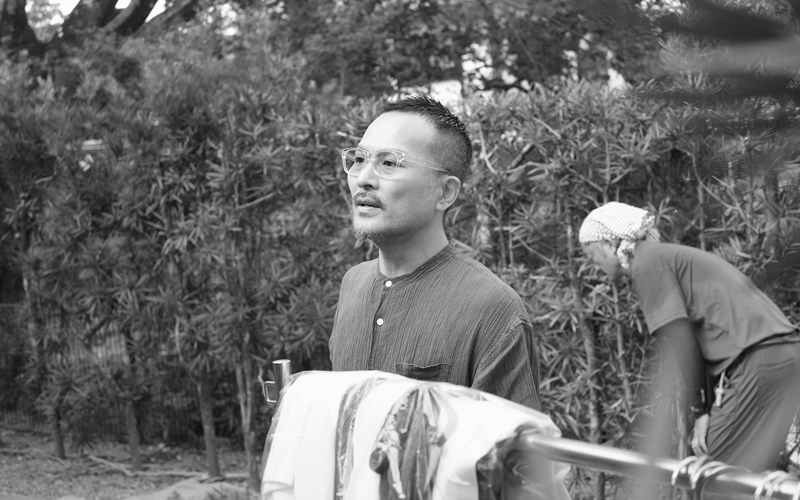
– 和モダン –
和物、日本や京都にある”モノ”を利用しながら現代的に表現する流れと、友禅などの図案をそのまま使う、あるいは少しアレンジして使う流れが混在していたこの頃、西洋にばかり向かっていた意識が一巡し、当たり前だった世代と知らない世代が同居する”和”を使ったムーブメントが起こっていた。
前者はポップでカラフルさが目新しく女性的。
あくまでも主役は今で、過去をサンプリングして使うスタイル。
後者は伝統を重んじる職人を感じさせ男性的。
過去の継承に自分の生活を合わせていくスタイル。
それは衣類や雑貨類だけに及ばず、食器や着物といったものにも広がり始め、前話の銀座店1階を使った”現代的な和モダン”の流れを読んだプロモーション。全く無知だった物を知った時の驚きは衝撃に変わる。
SOU・SOUさんが全面に打ち出されたこの大盛況な1階の衝撃、この出来事が私の脳裏に今でも残っているのは、もう一つ理由がある。ブランドなのかデザイン会社が打ち出していたプロダクトなのかはわからないが、思わず”可愛い!””発想力がすごい!”となるプロダクトを目にしたからだ。
それは銀細工で作られたハリネズミの背中に、苔玉を乗せたプロダクト。
派手な装飾は一切ない、白で固められたブースにポツンとそれは置かれていたにも関わらず、強烈な存在感を放っていて、針の筵のような緑色の苔がシルバーのハリネズミの意匠と合わさり最適化され、銀座の街を歩く老若男女の足を止めていた。
余談になるが、私が目にしたプロダクトは今はなくなってしまい、私の知るハリネズミと現在販売されているのは全く別物である。
引っ切り無しにSOU・SOUの地下足袋とハリネズミに人が集まり、レジと売場をスタッフが走り回る1階。それに比べて我々がいるフロアの寂しさといったらなかった。いや正しくはフロア自体の集客はあるのだけれど、我々のブースだけが閑古鳥である。
己の力の無さと情報力の乏しさを憂い、彼らや三越に感服した。

全館あげて”和物”を打ち出していたこと知った私は、パイプハンガーにかかっていた京友禅の図案を使った商品を前面に出すよう変更する。するとどうだ、1階のようにとはならないが、商品を手に取り、鏡で合わせてもらえる頻度が増えていく。
それに併せて友禅をあしらう前の無地Tシャツにも興味を持ってもらい始め、見せ方をまた一つ、また一つと変えながら覚えていく。今までどんよりと停滞していた山城ブースは流れを掴み始め、できることが増えていった。
こうして会期の1週間が過ぎ帰社すると、矢継ぎ早に求められるのは売上報告だ。街の空気感を感じながら練り歩くことや、現場の大切さや知らないことを吸収してお腹いっぱいの私と、数字だけを見て状況のみを詰めてくる社長。
確かに結果は散々たるマイナスな数字。
しかし買わないまでもDMを貰ってくれた人、無地Tシャツ1枚だけでも買ってくれた人など、数字には表れない現場での切磋琢磨があったのは明白だ。これは山城だけじゃなく、多くの会社が抱えるジレンマでもあると思う。
いつも埋まりそうで埋まらない立場上の溝だろう。
実際、強い意識を持っていたかどうかは数字だけでは見えづらい。
そんな風に見えなくても、目的を持って来店された方は爆買いをするし、売れるかもと思っていても冷やかしだけだったり、次への繋がる種蒔きの場合もある。
これはもうタイミングと言ってしまえばそれまでであるが、人の心は目に見えないから難しく、思うようにはいかないのだ。
今でこそ2〜4人体制で回し、ブース設営から販売、撤収まで一貫して背負ってくれる精鋭スタッフが各催事を支えてくれるまでになった。
スタッフが終業時の売上報告で申し訳なさそうに話しても、数字が取れなかった事情が”そこにあった”ことが想像できる信頼関係が築けるようになった。今回の話のように、自分自身が1週間、売場に立ち続けることを何年も経験して、やっと手に入れた技量といったところだろうか。
それは今でも変わることなく、私も3〜4日間は売場に立つ。
これぞ山城イズムとでもいうのか”こだわり”なのか。
温度感を把握しておきたい性分なのか。これは短い時間であっても売場に立ってくれるスタッフには、山城の人であって欲しいという想いを自ら伝えるための行動でもある。
商品を伝える誠実さ、懐にスッと入り込む器用さ、暑苦しくなくクロージングまで持っていける押しの強さなど。私が全てできる訳ではないが、全国百貨店をまわり、接してきたスーパー販売員からの学んだという自負もある。
やってみせ、言って聞かせてという有名な訓示ににもある通り、やってみせるまでは自分が出来ていないと話にならない。何事もそこから逃げていては始まらない。
今でも隙間で店頭や催事でお客様と接するのは楽しい。
余計なことを言ってしまった、今の言葉で決まったなどの反省や自信がダイレクトに売上に直結する臨場感が好きなんだろう。京都では海外からのお客様も多く来店されるから、あの頃の身振り手振り英語は相変わらずだが、少しづつ”出来る”が増えていく。
やはり現場は私にとって、昔も今も大切な場所である。